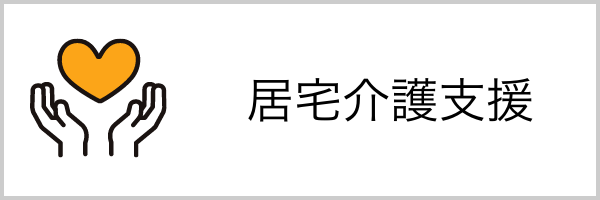ごあいさつ
平素より格別のお引き立てを、ありがとうございます。
われわれは、安心・安全・高品質なサービスを追求し、ご利用者様はもちろんのこと、
ご家族の方々にもご満足いただけるサービスを目指してまいります。
今後とも、みなさまのご期待に応えるべく、全社員で邁進していく所存であります。
お知らせ・更新情報
2025年2月21日 重要事項説明書掲載いたしました。
重要事項説明書
〔2024 年 9 月 1 日 現在〕
1. 当事業所が提供するサービスについての相談窓口
電 話 (03-5935-7043) (月~金曜日 9:00~18:00)担 当 介護支援専門員 渡邉 健一 /管理責任者 飯澤 康雅
※ ご不明な点は、何でもおたずねください。
※ 24 時間連絡体制を確保しております。
2. 居宅介護支援事業所の概要
(1) 居宅介護支援事業所の指定番号およびサービス提供地域
事業所名所在地
事業所の指定番号サービスを提供する実施地域※
居宅介護支援事業所エクラス(笑暮らす)東京都練馬区大泉学園町6-16-31
指定居宅介護支援事業 ( 東京都 第1372013845号)練馬区全域、新座市。
※上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。
(2) 事業所の職員体制
管理者 1名 介護支援専門員(管理者兼務含む) 1名以上
(3) 営業時間
月~金曜日 午前9時から午後6時まで
※ (土曜、日曜・祝日及び12月30日~1月3日)
(4) 事業計画及び財務内容について
事業計画及び財務内容については、利用者及びその家族にとどまらず全ての方に対し、求めがあれば閲覧することができます。
3. 居宅介護支援申込みからサービス提供までの流れ付属別紙2「サービス提供の標準的な流れ」参照
4. 利用料金
(1) 利用料(ケアプラン作成料)
要介護または要支援認定を受けられた方は、介護保険から全額給付されるので自己負担はありま
せん。ただし、保険料の滞納により法定代理受領ができなくなった場合、1ヶ月につき要介護度に応じて下記の金額をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。このサービス提供証明書を後日保険者の
窓口に提出しますと、全額払戻を受けられます。
(2)交通費
前記2の(1)のサービス提供地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地域の方は、介護支援専門員がお訪ねするための交通費の実費が必要な場合があります。
(3)解約料
お客様はいつでも契約を解約することができ、一切料金はかかりません。
(居宅介護支援利用料)
①要介護1・2 12,380円 要介護3・4・5 16,085円
②加算を算定した場合
・初回加算 1ヶ月につき 3,420円
※新規に居宅サービス計画を作成する場合。要支援者が要介護認定を受け居宅サ-ビス計画を作成する場合。要介護状態が2区分以上変更で居宅サービス計画を作成する
場合。
・入院時情報連携加算(Ⅰ)1ヶ月につき 2,850円
※利用者が入院するに当たって医療機関の職員に対して必要な情報を提供した場合に算定。(提供方法は問わない)月に1回を限度。
入院した日の内に提供を行う。入院日以前の情報提供を含み、営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合は、入院日の翌日を含む。
・入院時情報連携加算(Ⅱ)1ヶ月につき 2,280円
※利用者が入院するに当たって医療機関の職員に対して必要な情報を提供した場合に算定。(提供方法は問わない)月に1回を限度。
入院した日の入院した日の翌日又は翌々日に提供を行う。入院以前の情報を含み、営業時間終了後に入院した場合であって、入院日から起算して3日目が営業日で無い場合は、その翌日を含む。
・退院・退所加算(Ⅰ)イ 入院または入所期間中1回を限度に 5,130円
・退院・退所加算(Ⅰ)ロ 入院または入所期間中1回を限度に 6,840円
・退院・退所加算(Ⅱ)イ 入院または入所期間中1回を限度に 6,840円
・退院・退所加算(Ⅱ)ロ 入院または入所期間中1回を限度に 8,550円
・退院・退所加算(Ⅲ) 入院または入所期間中1回を限度に 10,260円
※医療機関や介護保険施設等を退院・退所し居宅サービス等を利用する場合において、退院・退所にあたって医療機関等の職員と面談を行い、利用者の関する調整を行った場合に算定。加算Ⅲを算定できるのは、そのうち1
回以上は入院中の担当医との会議に参加し、在宅療養上必要な情報交換も行い調整を行った場合に限る。
初回加算を算定する場合は算定しない。
・緊急時等居宅カンファレンス加算 1ヶ月に2回を限度 2,280円
※病院の求めにより、病院の医師または看護師等とともに利用者の居宅を訪問し、
カンファレンスを行い、必要時応じて利用者に必要な居宅サービスの利用に関する調整を行った場合に算定。1月に2回を限度として算定。
・ターミナルケアマネジメント加算 4,560円
※医師が一般的に認められている医学的見地に基づき回復の見込みが無いと診断され
た(終末期)利用者(在宅訪問後24時間以内に在宅以外で亡くなった場合を含む)が対象。24時間連絡が取れる体制を確保し、必要に応じて指定居宅介護支援を行う事ができる体制を整備。利用者またはその家族の意向
を把握、同意を得た上で死亡日
14日以内に2日以上在宅を訪問し、主治医等の助言を得つつ利用者の状態やサービス変更の必要性の把握、利用者への支援を実施。訪問により把握した利用者の心身の状況などの情報を記録し、主治医等及びケアプランに
位置付けた居宅サービス事業所への提供を行う。
・通院時情報連携加算(1ヶ月に1回を限度) 570円
※医師の診察を受ける際に同席し、医師または歯科医師に利用者の心身の状況や生活環 境の必要な情報提供を行い、医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サ-ビス計画に記録した場合。
・特定事業所医療介護連携加算 1,425円
※特定事業所Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得し退院・退所加算の算定に係る医療機関等と連携を年間35回以上行い、ターミナルマネジメント加算を年間15回以上
算定。
特定事業所加算(Ⅰ) 1ヶ月につき 5,916円
※下記の①~⑬までを満たす事。
特定事業所加算(Ⅱ) 1ヶ月につき 4,799円
※下記の②、③、④、⑥~⑬を満たす事。
※常勤専従の主任介護支援専門員を 1 名以上配置。
(主任介護支援専門員含め、合計 4 名以上)
特定事業所加算(Ⅲ) 1ヶ月につき 3,682円
※下記の③、④、⑥~⑬を満たす事。
※常勤専従の主任介護支援専門員を 1 名以上配置。
※常勤専従の介護支援専門員を 2 名以上配置。
特定事業所加算(A) 1ヶ月につき 1,299円
※下記の③、④、⑥~⑬を満たす事。
※常勤専従の主任介護支援専門員を 1 名以上配置。
※常勤専従の介護支援専門員を 1 名以上配置。
〇特定事業所加算の算定要件①~⑬
① 常勤専従の主任介護支援専門員を2名以上配置。
※提供に支障がない場合は、他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある指定介護予防支援事業所の職務と兼務可。
② 常勤専従の介護支援専門員を3名以上配置。
※提供に支障がない場合は、他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある指定介護予防支援事業所の職務と兼務可。
③ サ-ビス提供の為の留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的
(概ね週1回以上)に開催。
④ 24時間連絡体制の確保と必要時に利用者等の相談に応じる体制の確保。
⑤ 算定月の要介護3~5の割合が40%以上。
⑥ 計画的な研修の実施。
⑦ 地域包括支援センタ-から紹介の困難事例に対応。
⑧ 家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、
難病患者等、高齢者以外の対象者に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加。
⑨ 居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の適応を受けていない事。
⑩ 介護支援専門員1人当たりの担当件数が45件未満。
⑪ 実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保している事。
⑫ 他法人が運営する居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施している事。
⑬ 必要に応じて多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサ-ビス(インフォ-マルサービスを含む)が包括的に提供されるような 居宅サービス計画を作成。
5. 居宅介護支援の提供にあたっての留意事項について
1. 質の高いケアマネジメントの推進
・当該事業所の居宅サ-ビス計画(ケアプラン)総数に利用を位置付けた各サ-ビスの割合。
(※訪問介護、通所介護、地域密着通所介護、福祉用具貸与)
・前 6
月間に作成した居宅サ-ビス計画(ケアプラン)に位置付けた訪問介護、通所介護、地域密着通所介護、福祉用具貸与の提供回数のうち、同一事業所によって提供された割合を文書で交付し、介護サービス情報公表制度にお
いて公表します。
※令和6年度の介護保険改正にて努力義務となります。
2. 医療と介護の連携強化
病院等に入院しなければならない場合には、退院後の在宅生活への円滑な移行を支援等するため、早期に病院等と情報共有や連携をする必要がありますので、病院等には担当する介護支援専門員の名前や連絡先を伝えてくだ
さい。
3. 感染症対策の強化
委員会の開催(おおむね6月に1回)、指針の整備、研修の実施、訓練(シュミレ-ション)を定期的に実施します。
4. 業務継続に向けた取組の強化
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サ-ビスが継続的に提供できる
体制を構築する為、業務継続計画等(BCP)の策定、研修や訓練(シュミレ-ション)の実施、業務継続計画の見直しや変更等を行います。
※感染症若しくは災害のいずれか、又は両方の業務継続計画が策定していない場合は 100分の1に相当する単位数が減算になります。
(業務継続計画未策定減算:令和7年4月より)
5. 高齢者虐待防止の措置
利用者の人権の擁護、虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
⑴ 虐待防止に関する担当者及び責任者を選定します。
虐待防止に関する責任者 管理者 飯澤 康雅虐待防止に関する担当者 管理者 飯澤 康雅
⑵ 成年後見制度の利用を支援します。
⑶ 苦情解決体制を整備していきます。
⑷ 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施します。
⑸ 虐待の防止のための対策を検討する委員会を設置します。
⑹ 虐待の防止のための指針を作成します。
※虐待の発生又はその再発を防止するための措置(委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること)が講じられていない場合は100分の1に相当する単位数が減算になります。(高齢者虐待防止措置未実施
減算)
6. ハラスメント対策の強化
男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業員に周知・啓発します。
また相談や苦情に応じ、適切に対応するための窓口を定め、適切なハラスメント対策を行います。
7. 生活援助の訪問回数の多い利用者等への対応。
区分支給限度額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サ-ビスの大部分を占める等のケアプランを作成する居宅介護支援事業所を事業所単位で抽出するなどの点検・検証の仕組みを令和3年10月から導入済み。
8. 会議や多職種連携における ICT の活用
感染防止や多職種連携の促進の観点から、利用者等が参加せず、医療・介護の関係者のみで実施するものについて「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」及び「医療情報システムの安全
管理に関するガイドライン」等を参考にして、テレビ電話等を活用しての実施が可能になります。
利用者等が参加して実施するものについて、上記に加えて、利用者等の同意を得た上で、テレビ電話等を活用しての実施も可能になります。
9. 利用者への説明・同意等に係る見直し
利用者の利便性向上や介護サ-ビス事業者の業務負担軽減の観点から、政府の方針も踏まえ、ケアプランや重要事項説明書等における利用者等への説明・同意等のうち、書面で行うもの(交付、説明、同意、承諾、その他こ
れらに類するもの)について、承諾を得て、電磁的な対応が可能。
10. 記録の保存等に係る見直し
介護サ-ビス事業者における諸記録の保存・交付等について、原則として、電磁的な対応を認められます。(例:重要事項説明書、事業者等の連絡調整に関する文書・居宅介護支援台帳、区への通知に係る文章、苦情内容等
の記録・事故の状況及び処置についての記録等)
11. CHASE・VISIT 情報の収集・活用と PDCA サイクルの推進
CHASE・VISIT を活用した計画の作成や事業所単位での PDCA
サイクルの推進、ケアの質の向上を推奨。(個別機能訓練加算、リハビリテ-ションマネジメント加算、栄養管理、口腔管理等の利用者単位の個別領域のデ-タを使用し、計画・実行・評価・改善をサイクルしていく流れに
なります)
※居宅介護支援としては各利用者のデ-タ及びフィ-ドバック情報のケアマネジメントへの活用を推奨。
※令和3年度から、CHASE・VISIT を一体的に運用するにあたり、科学的介護の理解と浸透を図る目的から、統一した名称 LIFE(ライフ)を活用します。
※LIFE(ライフ):科学的介護情報システム
12. 看取り期におけるサ-ビス利用前の相談・調整等に係る評価
居宅サ-ビス等の利用に向けて介護支援専門員が利用者の退院時等にケマネジメント業務を行ったものの利用者の死亡によりサ-ビス利用に至らなった場合に、モニタリングやサービス担当者会議における検討等必要なケア
マネジメント業務や給付管理のための準備が行われ、介護保険サ-ビスが提供されたものと同等に取り扱う事が適当と認められるケ-スについて、居宅介護支援の基本報酬の算定が可能。
13. 身体拘束等の適正化の推進
利用者又はほかの利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならないこととし、身体的拘束等を行う場合には、その様態及び時
間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録致します。
14.第三者による評価の実施状況
当事業所の第三者による評価の実施状況は次の通りです。 〇第三者による評価の実施状況 1 あり 2 なし
実施日:
評価機関名称:
結果の開示: 1 あり 2 なし
6. 秘密保持
1 事業者、介護支援専門員および事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
2 事業者は、利用者の有する問題や解決すべき課題等についてのサービス担当者会議において、情報を共有するために個人情報をサービス担当者会議で用いることを、本契約をもって同意とみなします。
7.事故発生時の対応等
事業者、介護支援専門員又は従業員が、居宅介護支援を提供する上で事故が発生した場合は、速やかに区市町村及び利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
事故が生じた際には、その原因を解明し、再発防止の為の対策を講じます。事業所に連絡するとともに、利用者の主治医等又は医療関係への連絡を行い、医師の指示に従います。
8. サービス内容に関する苦情
(2) 当事業所の相談・苦情窓口
*居宅介護支援事業所エクラス(笑暮らす) 担当 飯澤 康雅 TEL
03-5935-7043当事業所の居宅介護支援に関するご相談・苦情および居宅サービス計画に基づいて提供している各サービスについてのご相談・苦情を承ります。
担当介護支援専門員または管理者までお申し出ください。また、担当介護支援専門員の変更を希望される方はお申し出ください。
(3) その他の窓口
当事業所以外に区市町村の窓口等に苦情を伝えることができます。
☆練馬区介護保険課(練馬区役所内) TEL 03-3993-1111(代表)
☆練馬区保健福祉サ-ビス苦情調整委員 TEL 03-3993-1344
☆練馬区内地域包括支援センタ- (別紙 1 を参照)
☆東京都国民健康保険団体連合会 TEL 03-6238-0177
(月~金 午前9時~午後5時)
☆新座市役所介護保険課(新座市役所内) TEL 048-477-1111(代表)
☆新座市高齢者相談センタ- (別紙 1 を参照)
☆埼玉県国民健康保険団体連合会(苦情相談専用)TEL 048-824-2568
(月~金 午前 8 時 30 分~正午、午後 1 時~午後 5 時)
(4) 苦情処理手順方法
① 苦情の申立書を受付ける
② 当事業所が苦情に関する調査を行う
③ その調査結果を受けて事業所が改善すべき事項を検討する
④ 改善すべき事項をもとに当該事項に関する指導を実施する
⑤ その結果を利用者又はそのご家族へ報告する
9.「書面掲示」
事業所内での「書面掲示」だけでなく、運営規定の概要等の重要事項について、
インタ-ネット上の情報の閲覧が完結するよう、「書面掲示」に加え、原則として重要事項等の情報をウェブサイト(法人のホームページ等又は情報公表システム上)に掲載・公表します。(令和 7
年度から義務付け)
10. 当法人の概要
法人種別・名称 合同会社 H.P.R
資本金 2,500,000 円(資本準備金含まず)
設 立 2021 年 9 月 1 日所在地・電話
代表社員 長谷川 博司
電話 090-2143-4620
事業内容 介護保険法に基づく居宅サービス事業
介護保険法に基づく居宅介護支援事業
障がい者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障がい福祉サービス事業
(別紙1)
〔2024 年 9 月 1 日 現在〕
練馬区 地域包括支援センター 一覧
センター名 所在地 電話番号 担当地域
第 2 育秀苑 羽沢 2-8-16 03-5912-0523 旭丘、小竹町、羽沢、栄町
桜台 桜台 2-2-4 03-5946-2311 桜台
豊玉 豊玉南 3-9-13 03-3993-1450 豊玉中、豊玉南
練馬 練馬 2-24-3 03-5984-1706 練馬
中村かしわ 中村 2-25-3 03-5848-6177 中村、中村南、中村北
練馬区役所 豊玉北 6-12-1 03-5946-2544 豊玉上、豊玉北
中村橋 貫井 1-9-1 03-3577-8815 貫井、向山
北町 北町 2-26-1 03-3937-5577 錦、北町 1~5、8、平和台
北町はるのひ 北町 6-35-7 03-5399-5347 氷川台、早宮、北町6、7
田柄 田柄 4-12-10 03-3825-2590 田柄 1~4、光が丘 1
練馬高松園 高松 2-9-3 03-3926-7871 春日町、高松 1~3
光が丘 光が丘 2-9-6 03-5968-4035 光が丘 2、4~6、旭町、高松 5
丁目 13~24 番
光が丘南 光が丘 3-3-1-103 03-6904-0312 高松 4、5 丁目 1~12 番、田柄 5、光が丘 3・7
第 3 育秀苑 土支田 1-31-5 03-6904-0192 旭町、土支田 1~4、高松 6
練馬ゆめの木 大泉町 2-17-1 03-3923-0269 谷原、高野台 3~5、三原台、石神井町 2
高野台 高野台 1-7-29 03-5372-6300 富士見台、高野台 1・2、南田中 1~3
石神井 石神井町 3-30-26 03-5923-1250 石神井町 1・3~8、石神井台 1・3
フローラ石神井公園 下石神井 3-6-13 03-3996-0330 下石神井、南田中 4・5
第二光陽苑 関町北 5-7-22 03-5991-9919 石神井台 2・5~8関町東 2、関町北 4・5
関町 関町南 4-9-28 03-3928-5222 関町北 1~3、関町南 2~4、立野町
上石神井 上石神井 1-6-16 03-3928-8621 上石神井、関町東 1、関町南 1
上石神井南町、石神井台 4
やすらぎミラージュ 大泉町 4-24-7 03-5905-1190 大泉町 1~4
大泉北 大泉学園町 4-21-1 03-3924-2006 大泉学園町 4~9
大泉学園通り 大泉学園町 3-53-1 03-5933-0156 大泉学園町 1~3、大泉町 5・6,東大泉 3(52 番~55 番、
58 番~66 番)
南大泉 南大泉 5-26-19 03-3923-5556 西大泉、西大泉町、南大泉 5・6
大泉 東大泉 1-29-1 03-5387-2751 東大泉 1・2、東大泉 3(1 番
~51 番、56 番~57 番)、東大泉 4~6
やすらぎシティ 東大泉 7-27-49 03-5935-8321 東大泉 7,南大泉 1~4
〔2024 年 9 月 1 日 現在〕
新座市 高齢者相談センター
センター名 所在地 電話番号 担当地域
東部第一
高齢者相談センタ- 新座市片山 1-9-1 048-480-5853 池田、道場、片山、野寺
東部第ニ
高齢者相談センタ- 新座市馬場 1-2-35 048-480-7808 畑中、馬場、栄、新塚
西部高齢者相談センタ- 新座市野火止 4-14-20 048-477-1707 丁目本多、あたご、菅沢、野火止(1~4)
西堀・新堀 新座市新堀 1-13-5 042-497-8106 西堀、新堀
高齢者相談センタ-
南部高齢者相談センタ- 新座市堀ノ内 2-9-31 048-487-8263 石神、栗原、堀ノ内
北部高齢者相談センタ- 新座市東北 2-1-17 048-486-5011 東北、東
野火止 5~8 丁目 高齢者相談センタ- 新座市野火止 6-16-15 048-485-8936 野火止 5~8 丁目
北部第二
高齢者相談センタ- 新座市新座 3-3-20-101 048-485-8587 中野、大和田、新座、北野
(別紙 2)
介護現場におけるハラスメント指針
居宅介護支援事業所
エクラス(以下「事業者」といいます)は、職員の尊厳と適切な労働条件を維持していくため、利用者及びその家族(以下「利用者等」といいます)によって職員に対し、以下の表またはそれに相当するハラスメント行為が
行われ、その事実が確認された場合、事業者は利用者等に対し以下の通りの対応を取ります。
1.ハラスメント行為について
1)身体的暴力
身体的な力を使って危害を及ぼす行為。(職員が回避したため危害を免れたケ-スを含む。
例:〇コップをなげつける〇蹴られる
〇手を払いのけられる
〇たたかれる
〇手をひっかく、つねる
〇首を絞める
〇唾を吐く
〇服を引きちぎる
〇お茶等を掛ける 等
2)精神的暴力
個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為。
例:〇大声を発する
〇怒鳴る
〇職員への差別的発言
〇威圧的な態度で文句を繰り返す
〇刃物をちらつかせる
〇「この程度できて当然」と理不尽なサービスを要求する
〇職員の説明等に耳を傾けず、理不尽な主張や要求をする
〇謝罪、土下座、正座等の強要
〇契約内容以外のサ-ビスの強要
〇職員に対しての嫌がらせ
3)セクシャルハラスメント
意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的な嫌ないやがらせ行為。
例:〇必要もなく手や腕、体をさわる
〇必要もなく職員の体を抱きしめる
〇性的画像・映像を見せる
〇卑猥な言動を繰り返す
〇無関係に下半身を露出する
〇職員の衣類の中に手を入れる 等
4)次の場合は「ハラスメント」に該当しないため留意します。〇認知症等の病気または障害の症状として現れた言動。
・認知症の行動症状(暴力、暴言、徘徊、拒絶、不滅行為等)・心理症状(抑うつ、不安、幻覚、妄想、睡眠障害等)のこと。
・病気又は障害に起因する暴言・暴力であっても、職員の安全に配慮する必要があることには変わりがありません。事前の情報収集等(医師の評価等)を行い、事業所として、医師、行政等と連携する等による適切なケアを
提供します。
2.事業所の対応
〇事実確認・調査
当事業所では、職員の相談窓口を設置しています。上記のような行為の疑いがある場合、速やかに状況確認、聞き取り調査を実施し、事実を確認した上で、次の対応を実施します。
(1)サービスの停止・担当者の変更
ハラスメント行為を確認した際は、サ-ビスの停止、相談業務の停止、担当者の変更等、対応させていただく場合があります。
(2)契約の終了
内容が悪質な場合は、契約書第 12 条第 3 項に基づき、契約を終了することができます。
(3)公共施設への連絡
必要に応じ、警察、管轄行政機関等へ報告する場合があります。
3.ハラスメント防止への取組み
(1)職員への教育
ハラスメントを防止するために、職員に対し次の研修・教育を実施します。
①本指針の理解
②契約書・重要事項説明書の適切な説明方法の習得
③介護保険制度・サ-ビス契約内容に関する理解
④契約範囲外サ-ビスを提供しないことの理解
⑤サ-ビスマナ-・虐待防止・コミュニケ-ション技術の向上
(2)再発防止
法人はハラスメントが発生した場合は、速やかに再発防止に取り組みます。
以上
(別紙 3)
要介護認定前に居宅介護支援の提供が行われる場合の特例事項に関する重要事項説明書
利用者が要介護認定申請後、認定結果がでるまでの間、利用者自身の依頼に基づいて、介護保険による適切な介護サービスの提供を受けるために、暫定的な居宅サービス計画の作成によりサービス提供を行う際の説明を行い
ます。
1. 提供する居宅介護支援について
・ 利用者が要介護認定までに、居宅介護サービスの提供を希望される場合には、この契約の締結後迅速に居宅サービス計画を作成し、利用者にとって必要な居宅サービス提供のための支援を行います。
・ 居宅サービス計画の作成にあたっては、計画の内容が利用者の認定申請の結果を上回る過剰な居宅サービスを位置づけることのないよう、配慮しながら計画の作成に努めます。
・ 作成した居宅サービス計画については、認定後に利用者等の意向を踏まえ、適切な見直しを行います。
2. 要介護認定後の契約の継続について
・ 要介護認定後、利用者に対してこの契約の継続について意思確認を行います。このとき、利用者から当事業所に対してこの契約を解約する旨の申し入れがあった場合には、契約は終了し、解約料はいただきません。
・ また、利用者から解約の申入れがない場合には、契約は継続しますが、この付属別紙に定める内容については終了することとなります。
3. 要介護認定の結果、自立(非該当)または要支援となった場合の利用料について
要介護認定等の結果、自立(非該当)又は要支援となった場合は、利用料をいただきません。
4. 注意事項
要介護認定の結果が不明なため、利用者は以下の点にご注意いただく必要があります。
(1) 要介護認定の結果、自立(非該当)又は要支援となった場合には、認定前に提供された居宅介護サービスに関する利用料金は、原則的に利用者にご負担いただくことになります。
(2)
要介護認定の結果、認定前に提供されたサービスの内容が、認定後の区分支給限度額を上回った場合には、保険給付とならないサービスが生じる可能性があります。この場合、保険給付されないサービスにかかる費用の全額
を利用者においてご負担いただくことになります。
(別紙 4)
サービス提供の標準的な流れ
居宅サービス計画作成等サービス利用申込み
当社に関すること居宅サービス計画作成の手順、 サービスの内容に関して大切な説明を行います
居宅サービス計画等に関する契約締結
※利用者は区役所へ【居宅サービス計画作成依頼届出書】の提出を行っていただきます。(提出代行可能)
ケアマネジャーがお宅を訪問し、利用者の解決すべき課題を把握します
事 業 者 の 選 定当社と契約をするかどうかをお決めいただきます
地域のサービス提供事業者の内容や、料金等をお伝えし、利用するサービスを選んでいただきます
提供する居宅サービスに関して、居宅サービス計画の原案を作成します
利用者による サービスの選択
計画に沿ってサービスが提供されるようサービス提供事業者等とサービス利用の調整を行います
居宅サービス計画に沿って、サービス利用票、サービス提供票の作成を行います
♦ サ ー ビ ス 利 用 ♦
サービス利用に関して説明を行い、利用者やご家族の意見を伺い、同意をいただきます
利用者やご家族と毎月連絡をとり、サービスの実施状況の把握を行い、サービス提供事業者と連絡調整を行います
毎月の給付管理票の作成を行い、国保連合会に提出します
利用者の状態について、定期的な再評価を行います。また、提供されるサービスの実施状況の把握を行います。
居宅サービス計画の変更を希望される場合、必要に応じて居宅サービス計画の変更を行います
カスタマーハラスメントに対する基本方針
合同会社H.P.Rではお客様に寄り添った対応を心がけ、安心して介護サービスを提供できるよう心がけております。一方で、お客様からの常識を超えた要求や言動で、人格を否定または暴力・セクシャルハラスメント等の従業員の尊厳を傷つけられる行為は継続的なサービス提供・サービスの質の悪化を招く問題と捉えております。そのため、お客様に対して誠意を持って対応しつつも、お客様からこれらの行為を受けた際には、毅然とした態度で対応いたします。
当社は、これからもより多くのお客様やビジネスパートナーの皆様とともに、この取組みを通じて、お客様との関係性がより良いものになることを目的に、「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を作成しております。
ケアマネジャーとカスタマーハラスメントの現状
ケアマネジャーは、要介護者の生活を支えるために重要な役割を果たしています。しかし、近年その業務が様々な困難に直面していることが報告されています。その中でも特に深刻なのがカスタマーハラスメント、通称「カスハラ」の問題です。
カスタマーハラスメントの定義と特徴
カスタマーハラスメント(カスハラ)とは、顧客や利用者、またその家族などが提供者に対して行う不当な要求や嫌がらせ行為を指します。具体的には、過剰なクレーム、無理難題の押し付け、暴言や中傷といった行為が含まれます。
対象となる行為
厚生労働省による「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」の記載内容を基に当社では下記の内容に類する行為をカスタマーハラスメントと位置づけます。
・利用者様またはそのご家族による職員への暴力・暴言
・利用者様またはそのご家族による威圧・脅迫
・利用者様またはそのご家族による合理的範囲を超える時間的・場所的拘束
・利用者様またはそのご家族による過剰または不合理なサービス要求
・合理的理由のない謝罪要求
・合理的理由のない金銭補償の要求
・従業員に関する解雇等の社内処罰の要求
・社会通念上過剰なサービス提供の要求
・合理的理由のない事業所以外の場所への呼び出し
・従業員に対するプライバシーの侵害行為
・従業員に対するセクシュアルハラスメント
・従業員に対するその他各種のハラスメント
・SNSやインターネット上での誹謗中傷 等
カスタマーハラスメントへの対応
カスタマーハラスメント事案に関する相談窓口を設置いたします。
カスタマーハラスメント事案が生じた場合の対応体制を構築いたします。
カスタマーハラスメント事案が生じた場合、被害者の心のケアを最優先に努めます。
また、当社が悪質と判断した場合には、警察や弁護士に相談等したうえで、適切に対処いたします。
引き続きご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
2025年10月
合同会社H.P.R
代表社員 長谷川 博司